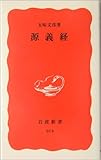和書 508066 (84)
![]()
武家と天皇―王権をめぐる相剋 (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
1942年生まれの日本中世史研究者が、天皇制存続の理由を問おうとして1993年に刊行した、近世統一権力成立期の朝幕関係を具体的に記述した本。院政期に権威・権力の頂点を迎えた天皇家は、大局的には承久の乱以降それらを段階的に喪失してゆき、南北朝合一期には、足利義満による皇位簒奪計画が成功の一歩手前まで達していた。しかしその後、交戦権の承認や叙任権の行使によって、戦国期には天皇の権威は徐々に回復し、信長ですら譲位強要には失敗した(28頁)。秀吉は長久手の敗戦で武力による東国征服(征夷大将軍位)を一時的に諦め、天皇権威に頼った天下統一を目指し、武家関白となったが、その結果彼は天皇の権威を絶えず引き合いに出さざるを得なくなった(律令制的な「王政復古」)。他方江戸幕府は公武の弁別に尽力し、天皇の権威の表出を嫌って、直奏禁止、家康の神格化(東照大権現)、紫衣事件、行幸制限等を通じて天皇封じ込め政策をとったが、官位による大名・寺社の序列化は廃棄しえず(権現号・将軍職も勅許による)、将軍が外交権を行使しつつ日本国王を自称しないことに見られるように、礼式世界の「奥の院」としての天皇権威を否定する論理を、ついに見出し得なかった。そのことを、著者は「俄の御譲位」事件の経緯において確認すると共に、明治維新が王政復古として現れる前提を成す事実として重視している。史料的制約ゆえか民衆の幕府・朝廷観が見えにくい点、長久手の戦いや女帝騒動のような個別の史実の歴史的意義を過大評価しているようにも見える点は気になるが、戦国期天皇の意外な権威の高さ、征夷大将軍職の意味、秀吉による王政復古・遷都計画など、興味深い史実を知ることができる。

平安王朝 (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
王家の一員にして藤原師輔の従兄の子たる満仲が、冷泉天皇(師輔外孫)擁護の立場から為平親王(同じく師輔外孫ではあるが源高明女婿)擁立阻止に動いたのが安和の変の真相であるという卓見に膝を打つ。
![]()
ベルリンの壁崩れる―移りゆくヨーロッパ (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
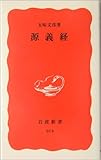
源義経 (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
著者五味文彦氏は、文献史学の第一人者。本書の狙いは、「源義経を鎌倉初期の政治史のなかで位置づけること」と筆者自身、あとがきに記している。残念ながらその目論見は成功しているとはいえない。
おそらく「岩波新書」という本として書かれた性格上、義経を中世政治史のなかに位置づけるということは、やはりはじめから難しかったというべきだ。
しかし、その中にあって、「Ⅴ」(第5章)の「義経の力」は、これまで文献史学の中でも見向きもされなかった義経文書について、考察が見られ、義経という人物の政治家としての資質が解き明かされるかもしれない。今後の研究成果が期待される。
筆者の「増補 吾妻鏡の方法」(吉川弘文館 増補版2000年11月刊)という野心的な研究書を見てきているだけに、ややアラカルト的な本書に物足りなさを感じてしまうのだろうか。
今まで、歴史学の著作で、そのものズバリ「源義経」のタイトルを付した代表的な著作といえば、安田元久、渡辺保両氏の二冊であろう。この二冊には、それぞれ
際だった特徴が見られる。読み手に歴史史料などは、まったく意識させず平明な言葉で、義経の生涯を情緒的にスケッチした安田版「源義経」。それに対し渡辺保版は、信頼できる史料のみを使って義経の実像のみを淡々と記した著作であった。この二冊とは、また違う切り口の新時代の「源義経論」が待望される。

明治維新と西洋文明―岩倉使節団は何を見たか (岩波新書 新赤版 (862))
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
明治初期、欧米各国を回った岩倉使節団の記録である。
尊王攘夷の思想を掲げ倒幕に走った志士たちは、維新の成就とともに自らが井の中の蛙であったことを知る。
そして、西洋文明を積極的に取り入れ、明治新政府を作り上げていく。
「先知ノモノ之ヲ後知ニ伝ヘ、先覚ノモノ後覚ヲ覚シテ、漸ヲ以テ進ム、之ヲ名ツケテ進歩ト云フ、
進歩トハ、旧ヲ舎テ、新キヲ図ルノ謂ニ非ルナリ、
・・・古人伝、百聞ハ一見ニ如カスト、寔ニ目視ノ感ハ、耳聴ノ感ヨリ、人ニ入ルコト緊切ナルモノナリ」
「百聞は一見に如かず」欧米諸国を目の当たりにした彼らの、まさにこれが率直な感想だったでろう。
そして、日本は徹底的に欧米諸国の模倣をしていく。
国の根本を支えていく教育から、法律、産業とありとあらゆる分野で欧米の知識を取り入れた。
この非常なる模倣の精神による摂取の中にこそ創造があり、日本は今日のような技術立国となりえたのである。
今ここに、改めて、明治期に今の日本に繋がる骨格を作り出した偉大な先人たちに敬意を表したい。

明治デモクラシー (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
この本の基本的な内容は、現在の日本近代史の図式が「明治憲法体制=天皇主権・専制政治、日本国憲法体制=国民主権・民主政治」という単純化された物であるとみなし、それに対して事実や資料を示すことで明治時代にも民主主義を目指す思想や運動が十分に存在した、と主張するものである。
自由民権運動についてはいちおう中高の歴史で学習はするものの、国会開設要求という程度にしか教えられていないのが現状であり、また著者が高く評価する福沢諭吉についてもその政治論が十分に知られているとは言い難いので、すでに明治期の歴史についての知識がある者にも有益な内容が含まれている。
また最終章の大正デモクラシーと吉野作造についての言及の中で、外来の思想に依拠する言説はより新しい外来の思想が出現すれば簡単に乗り越えられてしまう、外国ではなく日本における過去の思想から学ぶべきという著者の主張がある。大正時代についてのこの指摘は現在でも日本の社会科学にあてはまることであり、それについても考えさせられる。

邪馬台国論争 (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
本書は、20世紀100年間の邪馬台国論争史である。内藤湖南の学説を基軸として、さまざまな説の論点を明らかにしている。
内藤は、久米邦武が邪馬台国九州説に固執して、文献学的考証をないがしろにする論調を批判した。畿内大和説の内藤は、その論文「卑弥呼考」で〈卑弥呼神功旧説引戻し論〉として提示されたものである。ただ、ここでは卑弥呼は倭姫命に比定するという全く新たな説を立てている。
その後〈文献学的考証から考古学的研究へ〉時代は大きく変わっている。「考古学雑誌」に続々と登場した邪馬台国論。最近10年間は奈良・黒塚古墳出土の三角縁神獣鏡33面などから考古学を根拠に畿内説が勢いを増している。桜井市の箸墓は卑弥呼の墓。三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡。それらが根拠となりうるか。
ともあれ、本書は、内藤が論じた「卑弥呼考」に重点を置いて、前世紀100年の中での邪馬台国論の意義と、斯学への貢献が記述されている。

ユーゴスラヴィア現代史 (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
「民族浄化」やNATO軍による空爆などの悲惨な状況が、なぜ現代のヨーロッパにおいて生まれたのか。ボスニア内戦の構図を理解するのに有益な書。
著者もあとがきで記しているように、「現代史」と銘打ちながら、中世のセルビア王国やクロアチア王国などから紹介しており、南スラブ地域の通史でもある。このため、読み始めた当初は、第一次世界大戦後に成立した「第1のユーゴ」より前の、こうした歴史的記述部分はなかなか頭に入りにくく、ある程度読み進んだところで再度冒頭に戻って読み返すほどだった。
しかし、その結果、ボスニアに混住していたそれぞれの民族の歴史的な経緯や意識が、そのルーツである中世の「王国」時代から理解でき、チトー率いる「第2のユーゴ」解体から内戦に至る流れはしっかりと追うことが出来た。
セルビア人、クロアチア人、ムスリム人それぞれの歴史を丹念に追っているからこそ、「セルビア人悪玉論」に偏る「西側」の見方を超えた客観的な記述が出来たのだろう。地域、民族の歴史を踏まえた労作といえる。
![]()
ヨーロッパの心 (岩波新書 新赤版 (153))
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)
日本人が最も理解しにくいもののひとつが
キリスト教だろう。
著者は、深くそれに肉薄し、自らのものにしていらっしゃるようなので、
日本人のキリスト教受容の体験書として
価値があります。
でも、それ以外に、以下の3点で大きなマイナス面も含んでいます。
1)自慢話の羅列
日本人の多く(特に知識階層)は、ヨーロッパに行ってみないで、
住んでみないで、友を持たずに、
ヨーロッパなるものを語ろうとすることが多い。
しかし自分はいくつもの違った土地に行き、長く住み、
著名人を含む優れた友人を持ち、
多くの感動的なエピソードモ語ることができ・・
という話が、「わたしが」「わたしの」と頻出するので、
読んでいて、低級な思いになる。
2)結論ありきで、断定的にくだされ、基調になっているキリスト教礼賛
十分な説明がなく、なんとも唐突に、ありがたそうに語られるそれには
説得力が何もない
3)これがもっとも重要なのだが、「周辺を切り捨てた、直線的思考と価値観」
著者は、ヨーロッパは、ギリシャとローマとキリスト教でできている
と、何度も断定する。
だとしたら、キリスト教以前に広くその地を被っていたケルトの文化はどうなるのか。
ギリシャの隣にあって大きな影響力を持ったペルシャの存在は。
さらにギリシャの文化を持ち込んで、維持発展させたのは、むしろイスラム圏であり、
かれらの地中海文化への貢献は?
あるいはヨーロッパの母体ともなった森の文化といった地理的要因は・・などなど。
そうしたことがいっさい切り捨てられて、直線的に、3つを結びつけ、
価値観的にもつなげて他のことに口をつぐんでしまうのは、
まったく危険な思考を言わなくてはならない。
では、こういった内容の書物をどういう言葉で形容すればいいのか。
浮かんできたのは、ヒステリーという言葉だ。
すると、キリスト教を深く受容し、それを文化の基盤としたヨーロッパの
異端尋問や、魔女狩り、焚書、
異なる文化の人とその文化全体を抹殺した極端に野蛮な行為なども、
社会全体が引き起こした、ある歴史的文脈の中でのヒステリーなのだったのだなと
思えたりもする。
それがひとつのヨーロッパの心にもなってきたのだという歴史を思う。
キリスト教とヨーロッパを結びつけた書物ならば、
たとえば『ヨーロッパの四季』(饗庭孝男著)のような書物の方が
よほど好ましく、こころ楽しく読める。

ライン河―ヨーロッパ史の動脈 (岩波新書)
販売元: 岩波書店
Amazonのカスタマーレビュー(口コミ)